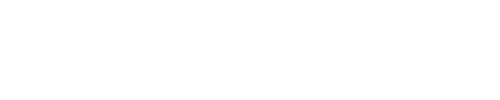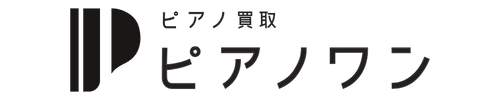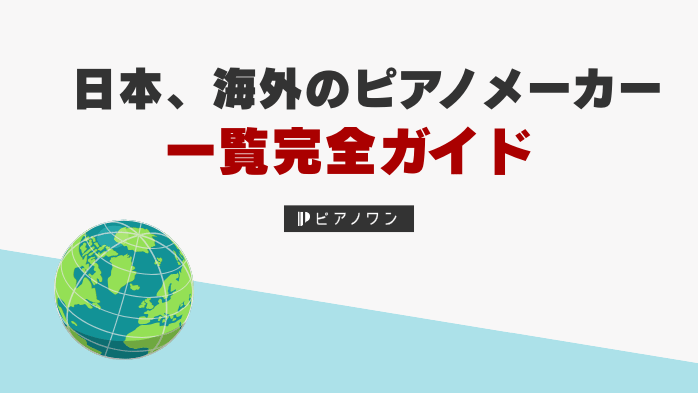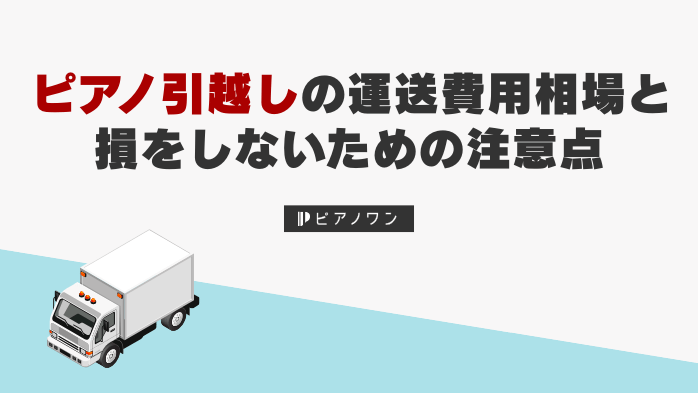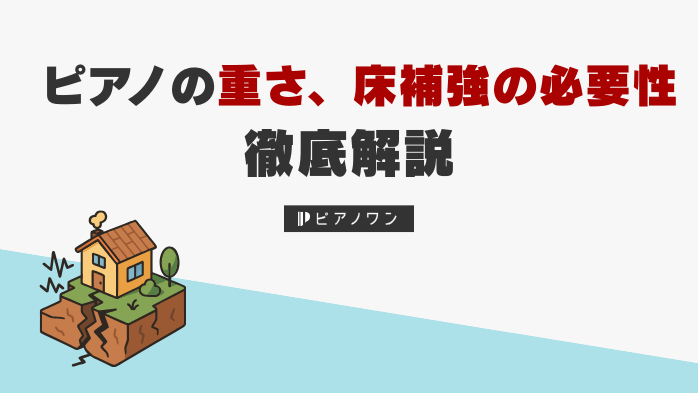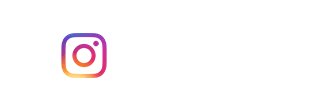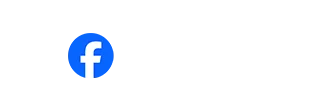スタインウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインの違いとは
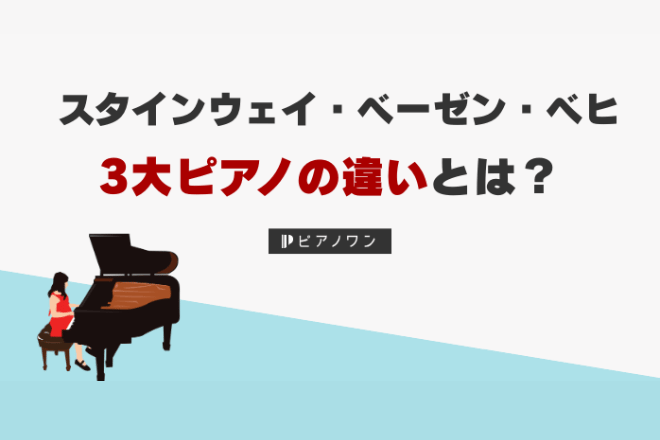
目次
皆様、ピアノを知っている方も、知らない方も、主要メーカーであるヤマハ・カワイはご存じあるかと思います。
ですが、海外メーカーで世界三大ピアノとされる、スタインウェイ&サンズ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインというピアノをご存じでしょうか?
今回は、そんな世界三大ピアノの違いについてご紹介させていただきます。
スタインウェイ&サンズ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインの違いを徹底比較
早速ですが、スタインウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインの各違いについて紹介していきます。
歴史の違い

スタインウェイ&サンズ
創業1853年。創業者は、ハインリッヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク(ヘンリー・エンゲルハード・スタインウェイ)が、スタインウェイ&サンズをマンハッタンのヴァリックストリートに設立。1857年にはピアノ構造上の特許第一号を取得しています。
1880年には、ドイツ・ハンブルクにも生産拠点を設置し、1903年生産台数10万台を突破。1938年には生産台数30万台を突破し、30万台目はホワイトハウスに贈られたという歴史があります。

ベーゼンドルファー
ベーゼンドルファー社が設立された1828年。創業者は、イグナツ・ベーゼンドルファーで、4代のピアノを製作しましたが、1835年にはその数は200台に増えていました。
また、1839年には、オーストリア皇帝はイグナツ・ベーゼンドルファーに、ピアノ製作技術者として初の栄誉である、『宮廷及び王室ご用達ピアノ製造技師』として、公式な称号を授与しています。

ベヒシュタイン
創業者は、カール・ベヒシュタイン。ロマン派の全盛期であった1853年にドイツ・ベルリンにてでベヒシュタイン社を設立しました。
1885年にはロンドン支店を設立。1900年頃には生産のピークを迎え、年間3,500台のピアノを生産しました。
アクションの違い
スタインウェイ&サンズ
スタインウェイのアクションは鍵盤の動きをそのまま正確に弦に伝える構造になっています。このアクションを支えているのが、木材を充填したチューブ方式のアクションフレームといわれるもので、ピアノを弾く際のエネルギーのロスを最小限に抑えてアクション全体が精密に機能することを実現しています。
このアクションフレームの働きにより、ピアニストの思いのままにタッチをコントロールできるという仕組みになっています。
ベーゼンドルファー
ベーゼンドルファーのアクションは、繊細なピアニッシモから壮麗なフォルテッシモまで、無限に広がります。それを生み出すアクションは、アーティストや技術者の協力を得て独自の仕様で製造されています。
コントロールしやすく、且つ扱いやすい優れたアクションは、アーティストの感情をダイレクトに聴衆に伝えるように造られています。
ベヒシュタイン
ベヒシュタインのアクションはカエデとシデというものから作られており、ハンマーは自由に動くため創造的なプロセスを損なうことがないように造られています。鍵盤に抵抗感となめらかさの理想的なバランスを追求し、このアクションは演奏者の打鍵の微妙な差を、正確に直感的に造作もなく反映するようになっています。
鍵盤の幅・長さ
スタインウェイ&サンズ
スタインウェイは鍵盤数は88鍵盤で、白鍵の前の部分の長さは約48.5mmで、他のピアノと比べて1mm短く作られています。
ベーゼンドルファー
ベーゼンドルファーには88鍵盤、92鍵盤、97鍵盤と3種類のモデルがあります。88鍵盤は他のピアノと変わらずですが、92鍵盤のピアノはヤマハC7クラスの大きさ、97鍵盤はヤマハのフルコンサートグランドピアノより15cm長い奥行きとなっています。
ベヒシュタイン
ベヒシュタインの88鍵盤が一般的で、白鍵の幅は22.3~22.8mm、黒鍵の幅は9.0~10.5mmが基準となっています。
鍵盤の重さは、スタインウェイが47g、ベヒシュタインが48gが世界の標準となっていますが、大差ない重さだと感じます。
音色の違い
スタインウェイ&サンズ
スタインウェイのピアノは濁りのない音色で知られており、高音は繊細でクリア、低音は力強く温かみのある響きがあります。ピアニストの指の動きをそのまま表現し、心にまで届く華やかな音色を奏でることができるのが特徴です。
ベーゼンドルファー
ベーゼンドルファーは持続音が長く、柔らかく温かみのある音色と、堂々とした響きの低音でありながら、鮮やかで天使のような高音が特徴です。
透明感と気品に溢れた柔らかい音色、鍵盤楽器ながらまるで大きな弦楽器のように、ピアノ全体から深く豊かな音を響かせることができるのが魅力です。
ベヒシュタイン
みずみずしい透明感と色彩豊かな音色と、歌うような雰囲気と珠玉の音色がありながらも、ダイナミックな力強さが特徴です。
繊細なピアニッシモから迫力のあるフォルテッシモまで、全音域に渡って旋律を美しく歌い、複雑な和音の中にあっても旋律部分が埋もれることのない透明な響きが魅力です。
以下でピアニストの森本様が弾き比べの動画を公開して頂いてますので、引用させて頂きました。是非一度ご視聴ください。
タッチの違い
スタインウェイ&サンズ
スタインウェイは、世界的に最も軽いピアノとして知られています。S-155~B211までの鍵盤の重さは、47gで設計されています。
その軽やかさや反応の良さに驚くとともに、表現したい音やタッチを演奏に表すことができる心地よさを感じるとされています。
ベーゼンドルファー
ベーゼンドルファーは、象牙からヒントを得た、タランという特許素材の鍵盤を使用することで、心地よい演奏感を実現しています。
ベヒシュタイン
ベヒシュタインは、音の立ち上がりが速く、タッチに瞬時に反応する打弦ピーク音からの減衰が早く、持続する音とされています。
愛用しているアーティスト
スタインウェイ&サンズ
・ビリー・ジョエル
・セルゲイ・ラフマニノフ
・ジョン・ボーニング
・アントン・ルビンシュタイン
・内田光子
・中村紘子
・角野隼斗
ベーゼンドルファー
・久元祐子
・スティーリー・ダン
・ヴィルヘルム・バックハウス
・オスカー・ピーターソン
ベヒシュタイン
・クロード・ドビュッシー
・フランツ・リスト
・アルトゥール・シュナーベル
・小野塚晃
有名なコンクールで使用されているメーカー
ショパン国際ピアノコンクール
世界三大ピアノコンクールの一つ目といえば、ショパン国際コンクールでしょう。最初期の開催回では、スタインウェイの他にベヒシュタイン、ベーゼンドルファーが使用されていました。ですが、2021年にはスタインウェイ(ハンブルグ製:製造番号479と300)、ヤマハ、カワイ、ファツィオリが使用されるようになり、ベーゼンドルファーが選ばれなかった理由としては、ヤマハ傘下であるため、国際的にも有名なヤマハが選出されたとされています。
エリザベート王妃国際音楽コンクール
世界三大ピアノコンクールの2つ目は、エリザベート王妃国際音楽コンクール。古くから世界的に有名な音楽家を輩出してきた、歴史と権威のある大会です。この大会でも、過去10回の優勝ピアノのうち9回がスタインウェイのピアノでした。一方で、ピアニストの務川慧悟氏は第3位を受賞しています。務川氏は、ベーゼンドルファーを使用して演奏されたようです。ベヒシュタインに関しても、本コンクール内で使用されたようです。
チャイコフスキー国際コンクール
世界三大音楽コンクールの3つ目は、チャイコフスキー国際コンクール。その名の通りで、ロシアの作曲家チャイコフスキーにちなんでいます。2015年にはマスレーエフ氏がスタインウェイD-274を使用して優勝されました。ファイナリスト達もスタインウェイを使用する方が多かったようです。一方で、ベーゼンドルファー・ベヒシュタインは使用されなかったようです。
販売価格の違い
スタインウェイ&サンズ
(ドイツ・ハンブルグ工場製)
S-155:15,895,000円
M-170:17,259,000円
B-211:23,606,000円
D-274:37,829,000円
ベーゼンドルファー
170VC:20,020,000万円
185VC:21,450,000万円
290:41,910,000万円
ベヒシュタイン
A.160:7,425,000万円
A.228:11,770,000万円
B-212:20,900,000万円
買取価格の違い
スタインウェイ&サンズ
Sタイプ:約200~300万円程度
Mタイプ:約250万円~300万円程度
Bタイプ:約300万円~1000万円程度
(年式により相場は変動いたしますのでご留意ください。)
ベーゼンドルファー
130タイプ:100~140万円程度
200タイプ:300~350万円程度
(年式により相場は変動いたしますのでご留意ください。)
ベヒシュタイン
Aタイプ:90~150万円程度
Bタイプ:90万円程度
(年式により相場は変動いたしますのでご留意ください。)
まとめ
今回は、スタインウェイ&サンズ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインの世界三大ピアノを深堀りさせていただきました。
筆者も実はベーゼンドルファーやベヒシュタインを試弾したことがありますが、やはり国内メーカーとは違う魅力があり、弾き心地や音色、質感がとても良かったと感じています。もちろん、国内メーカーの良さもたくさんありますので、あくまでこの記事をご参考程度に見ていただければ幸いでございます!
(よろしければこちらの記事(ヤマハとカワイの違いを解説|ピアノ徹底比較)もご覧くださいませ!)
ぜひ、一度試弾されてみてはいかがでしょうか?(試弾だけでも楽器店では無料でできるので、お勧めいたしますよ♪)
最後までお読みいただきましてありがとうございました!
買取業者として、皆様のピアノライフに寄り添えますように願っております…♪
営業所一覧
北海道・東北地方のピアノ買取一覧
関東地方のピアノ買取一覧
中部地方のピアノ買取一覧
近畿地方のピアノ買取一覧
中国地方のピアノ買取一覧
四国地方のピアノ買取一覧
九州地方のピアノ買取一覧
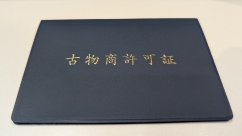
ピアノワンは大阪府公安委員会から買取に必要な古物商許可を受け運営しております。
【大阪府公安委員会古物商許可番号】 第62227R046045号
大阪府公安委員会ホームページ
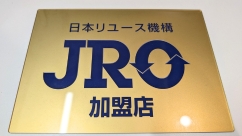
ピアノワンは一般社団法人日本リユース機構の準会員です。
一般社団法人遺品整理士認定協会ホームページ